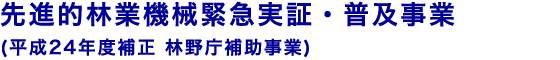【事業の内容について】
Q1. 導入・改良の対象となる機械はどのようなものですか。
- 対象となる導入・改良を行う林業機械については、事業規模ベースでの稼働や普及が行われていない先進的林業機械を想定しています。
- このような機械を事業規模ベースで稼働させつつ、機械メーカーや代理店等とともにサポート体制の構築に取り組み、機械の改良や改善に取り組むことが必要とされます。
- 同時に、事業期間内に取得・稼動が可能であるとともに、検証・評価を行うことができる機械である必要があります。
- 導入・改良の対象となる機械が具体的に定まっている場合は、パンフレットや見積書等を参考資料として申請書に添付してください。
- なお導入する林業機械及びそれにより構築する作業システムが事業の趣旨に適合するものであるかどうかについては、検討委員会において厳正な審査を行います。
Q2. 提案書に記載した機械メーカーや機械の機種について、事業実施時に変更することは認められるのでしょうか。
- 本事業においては、これらは申請内容の根幹に関わる問題となると思われます。そのため、変更は原則として認められないと思われます。
- 個別の事案については、当社設置の検討委員会に諮り判断することとなります。
Q3. 林地残材をバイオマス用途に集材するような作業システムについての提案も可能ですか。
- 提案内容にもよりますが、新規性のある林業機械・作業システムであればご提案いただくことは可能です。
Q4. オペレータの訓練についてはどのように実施すればよいのですか。
- 本事業出支援する取組では、導入する林業機械の継続的な使用を確実にするため、オペレータに操作技術やメンテナンス対応等の技術訓練を実施することができます。
- 訓練の内容、スケジュール等は、ご提案事項となります。導入する林業機械メーカーや販売店等と相談の上、事業趣旨に沿った訓練を企画ください。
Q5. 現地検討会や運営委員会はどのように実施すればよいですか。
- 構成員、開催回数・時期、議題等は、ご提案事項となります。
- 募集要領に記載された会議の目的に従い、事業内容およびスケジュールを考慮した事業の主要ステップで開催することが望まれます。
Q6. 現地検討会は具体的にはどのようなことをするのですか。
- 導入機械を用いた、素材生産などの作業システムのデモンストレーション、機械の機能や導入効果について紹介するミニシンポジウムを想定しています。
Q7. 運営委員会は具体的にはどのようなことをするのですか。
- 運営委員会は、林業事業体に加え、都道府県・森林管理局担当者、機械メーカー・代理店、試験研究機関などにより組織されます。
- この運営委員会にて、林業事業体は事業遂行にあたっての助言を得たり、取組の検証を行っていただきます。
Q8. 「研究機関」とは具体的には何を指しますか。
- 「研究機関」の例として、都道府県の林業試験場等、国の研究機関、大学、民間の研究機関などが想定されますが、特にその範囲は限定していません。
- 研究機関は、運営委員会にて、本事業の評価・分析の部分を担う、あるいはその部分に対して助言や情報提供を行うことが想定されます。したがって、その能力を有することが要件となります。
- また参画する研究機関は官民を問いません。
Q9. 応募申請にあたり、必ず研究機関等と連携する必要はありますか。
- 本事業では地域の実情に応じた事業規模ベースでの実証を行うことを重視しており、作業システムの開発・評価、データ収集・分析等を実施する必要があります。研究機関等との連携は必須ではありませんが、その場合は、取組の参画者のいずれかが、このような能力を有する必要があります。
Q10. 「データの収集・検証」とありますが、具体的にはどのようなことを指しますか。
- 本事業では、個別作業レベルでの機械の能力、サイクル作業レベルでの生産性の評価、現場単位での生産性の評価、経営レベルでの機械導入効果の検証を行う予定です。
- 提案書では、本事業で解決しようとする課題の設定、およびその課題解決の状況を検討するのに適した検証方法をご提案ください。
Q11. 合同会議は今年度のみの開催ですか。事業期間終了後5年間も出席を求められますか。
Q12. 事業実施中及び終了後の都道府県・森林管理局の役割はどのようなものですか。
- 交付決定を受けた事業者が実施する取組について助言を行うことや、事業者の取組を支援すること、都道府県下または森林管理局管内の事業体等に対して成果の広報や普及を支援すること等が役割と想定されます。
- 事業期間終了後は、取組の継続について支援を行うことが期待されます。
【申請書の作成・提出について】
Q13. 本事業で複数種の機械の導入を検討していますが、機械の種類ごとに申請書は必要ですか。
- 応募する林業事業体が1社であれば、導入機械ごとに申請書類を作成する必要はありません。申請書6ページ「先進的林業機械の内容・仕様・性能」の表を機械の種類に応じて増やして、それぞれ記載してください。
- 複数の林業事業体が共同で複数の機械を導入することを計画している場合は、そのうちの民間団体1社が代表して応募者となることで、必要書類1式で応募することができます。ただし、申請書の中で各機械の所有主体を明確にする必要があります。
Q14. 各種様式に記載されている「番号」とはどんな意味ですか。
- この番号は、文書管理のための通し番号を記載いただくという意味です。
- 本事業を行う上では原則として文書管理番号をつけてください。
Q15. 応募申請書の正1部と副7部について、すべてに押印は必要ですか。
- 副7部については、押捺した正本の複写を利用してご提出ください。
Q16. 提出書類のうち「⑤応募する事業体の活動実績・活動概要がわかる資料」について、決算書しかない場合、新たに事業報告書等を作成する必要はありますか。
- 決算書を作成されていましたら、それをご提出いただければ結構です。申請書「Ⅰ.申請者の概要」の当該欄に事業内容や実績等を詳細に記載ください。
Q17. 提出書類のうち「⑤応募する事業体の活動実績・活動概要がわかる資料」について、事業報告書、決算書等は何年分の提出が求められますか。
- 応募申請書類の提出にあたっては直近1年分でかまいません。
- ただし、必要に応じて事務局から複数年分の提出を求める場合があります。
Q18. 応募申請書を事務局に持参して提出することはできますか。
- 応募申請書類は郵便・宅配便での提出のみを受け付けています。なお、お送りいただく際には、書留等の配達記録が残る方法でお送りください。
【都道府県・森林管理局の推薦書について】
Q19. 都道府県・森林管理局の推薦が必要な理由を教えてください。
- 本事業では先進的林業機械を導入し、効率的な新しい作業システムを構築することとともに、その成果の普及を通じて、我が国林業の効率性や生産性を向上させることを目的としております。そのため、取組の実施および広報・普及が確実なものとなるよう、都道府県または森林管理局の主体的な参加を必要としています。
Q20. 都道府県・森林管理局の推薦が得られない場合は、応募資格を失うのでしょうか。
- はい。都道府県または森林管理局からの推薦が得られない応募者は、選定の対象となりません。
Q21. 都道府県・森林管理局から推薦を受ける手続きについて教えてください。
- 応募者が所在する都道府県の林業担当部署または森林管理局に直接お問い合わせください。
- 推薦書は提案書に添付してご応募ください。提案書発送までに推薦書の入手が間に合わない場合は、事務局にご相談ください。
Q22. 都道府県・森林管理局の推薦書は、具体的には誰の推薦が必要になりますか。
- 都道府県であれば本庁の林業担当部局の長、森林管理局であれば局長の推薦をお願いしています。
Q23. 都道府県・森林管理局が作成する推薦書には公印が必要ですか。
- 公印は不要です。各都道府県の林業担当部局の部局長名または、各森林管理局の局長名を記入して作成されていれば問題ありません。
- なお、推薦書の記載内容について、当社から担当者に問合せする場合があります。
【経費の積算について】
Q24. 経費が助成の対象となる期間はいつからいつまでですか。
- 交付決定通知日から平成26年2月14日(金)までが助成対象期間となります。
- 選定通知は5月下旬、交付決定通知は6月上旬となる予定です。やむを得ない事情があると認められた場合は、選定通知の受領後、届出により交付決定前の事業着手を行うことができます。
Q25. 助成金額に上限・下限はありますか。
- 必要な活動が実施できる経費が盛り込まれていれば、特段、上限・下限はありません。
- 20件程度のモデル事業体を選定し、助成金総額として10億円を目安としています。
Q26. 機械の購入費用の助成率はいくらですか。
- 本事業の助成額は定額です。機械の購入金額もご提案内容です。
Q27. 機械の改良費は助成経費に含まれますか。
- 含まれます。
- ただし、改良が終了し、機械を稼働させ、データ収集を実施することを年度内に終えることが必要です。
Q28. 今回導入を予定している機械は複数であり、それぞれ別のメーカーです。この場合、助成対象となるのは1社分の機械だけでしょうか。
- 本事業は1社分の機械に限定した助成を想定しているものではありません。
- ただし、助成対象となる機械は提案の内容や選定委員会での審査結果次第で判断されます。
Q29. オペレータ訓練に必要な旅費や謝金は助成経費に含めることができますか。
- オペレータ訓練に必要な旅費、謝金等の費用は、助成経費に含めることができます。
- 助成対象の内容や金額は、事務局及び検討委員会において査定の上、決定されます。
Q30. 事業期間終了後の報告に必要となる調査経費(専門家への謝金等)について、事業期間終了後の5年間分を今回の収支計画に積算することはできますか。
- 助成対象期間は交付決定日から平成26年2月14日までです。今回計上していただくのは、今年度実施分に限られます。事業期間後の経費については計上することはできません。
Q31. コンサルタント会社に事業地での調査やデータの収集作業にかかる経費を委託料として計上することはできますか。
- 業務の委託は可能です。ただし、その業務にかかる委託料は適切に積算され、請求されることが要件です。
- 委託する業務の内容とその成果物が明確であること、業務仕様を定めて委託契約を締結すること、委託業務を含む取組全体の進捗および成果について申請者が責任を負うことが前提です。業務の丸投げは認められません。
Q32. 普及啓発に関する告知業務にあたり、地方自治体に業務を委託することはできますか。また委託できる場合、その会場費や印刷代等の経費は積算することができますか。
- 地方自治体に対して業務の委託は可能です。ただし、その業務にかかる委託料は適切に積算され、請求されることが要件です。
Q33. 支出計画の作成にあたり、合同会議に関連する参加経費等はどの区分に積算すればよいですか。
- 「6. 取組推進のための運営委員会及び新作業システム等に関する現地検討会の開催」の区分に積算をお願いします。
Q34. 林業機械の損害保険料は助成対象になりますか。
Q35. 収入計画の「自己資金等」とは具体的にどのような内容を指すのですか。
- 本事業の助成対象とはならない支出を行う場合や交付金額が超過する事業費が必要となる場合に自己負担する経費を計上してください。
- 助成対象とならない経費の例としては、借入金の金利や損害保険料が挙げられます。
【その他】
Q36. 審査はどのように行われますか。
- 有識者により構成される選定委員会において、厳正な審査を行い選定します。
Q37. 選定件数はどれくらいですか。
Q38. 選定結果はいつ頃どのようにわかりますか。
- 選定結果については、5月下旬頃に、当社から応募者に文書により通知する予定です。
- 上記の文書以外では選定結果についてお知らせいたしません。お電話等による個別のお問い合わせには応じられませんのでご了承ください。
Q39. 募集の内容について詳しく知りたいのですが、どこに問い合わせればよいでしょうか。
- 本事業に関するお問合せは、株式会社自然産業研究所 先進的林業機械事業事務局にて承っております。本ページ下部のお問い合わせ先を参照ください。
- 林野庁森林整備部 研究指導課 技術開発推進室(TEL:03-3501-5025)でもお問い合わせに対応しております。
Q40. 応募要領や申請書類をダウンロードできないのですが。
Q41. 採択され、助成金の交付を受けた場合、支出等に関する報告義務はありますか。
- 助成を受けようとする全ての対象経費について報告の義務があります。
Q42. 本事業に参画する研究機関が本事業で収集した生産性等に関するデータを学術研究等に利用しても良いですか。
- 本事業の趣旨に基づき、データを活用しての学術研究や普及啓発活動は積極的に行ってください。
- ただし、実施主体の林業事業体に、データの利用について了承を得てください。
- また、各種報告や論文・雑誌といった、対外的に発信をされる場合には本事業の助成を得て実施した取組であることを明示してください。
- なお、本事業の実施主体である株式会社自然産業研究所や林野庁も各事業体から提供いただいたデータを普及啓発のために活用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Q43. 事業終了後の事業体の責務にはどのようなものがありますか。
- 事業終了後の5年間、当該取組の活動状況ならびに成果について報告していただきます。
- また、取組を通じて取得した財産や実績報告書に関係する会計書類等を適切に管理する必要があります。詳細については募集要領をご覧ください。